江戸から続く伊賀焼の窯元である「土楽」。
作陶を手がける福森雅武さん、道歩さん、
そしてたくさんの職人さんといっしょに
「ほぼ日」では「うちの土鍋」シリーズや、
「ほんとにおいしいカレー皿」などで、
いっしょにものづくりをしてきました。
この土鍋でつくったら、
さぞおいしいものができるにちがいない。
このお皿にのせれば、
いつものおかずが上等に変身するんじゃない?
ああ、このうつわに、あれを盛りたい。
食卓が、たのしくなるだろうなぁ、
みんなの笑顔が目に見えるよう──。
そんなことを思わせるのが、土楽のやきものです。
そして土鍋が鍋料理だけのためのものじゃない、
もっと、いろいろな料理がつくれるんだよ、と
教えてくれたのも土楽という窯元でした。
「土楽のふぞろい市」には、
規格を少しはずれたふぞろいな土鍋やお皿、取り碗など、
いろいろな陶器が特別な価格でならびます。
地元の伊賀では年に一度、
たくさんの窯元といっしょに開いている陶器市ですが、
東京では、はじめての試み。
じっさいに見て、手にとって、
毎日使う、ふだんのうつわにプラスする、
「うちに連れて帰りたいな」と思ううつわを
みつけていただけたらと思います。
会場には、土楽から福森道歩さんがやって来て、
料理人修行時代からの友人で、
いまは料理家やフードスタイリストとして活躍している
かたがたといっしょに店番をします。
土鍋料理のレシピや、土鍋やうつわごとの
盛り付け方のアドバイスを聞くこともできますよ。
お気軽に、どんどんお声がけください。
土楽ってどんなところ?

三重県の北西部、伊賀市の丸柱に、
伊賀焼の窯元「土楽」があります。
まわりには、田んぼや畑、鮎が釣れる川、
山菜やキノコがとれ、
ときには鹿やイノシシにであうこともあう山。
はるか昔、いまの琵琶湖のルーツである
「古琵琶湖」の底だったというこの地域には、
とても質のよい陶土が堆積していました。
奈良時代、聖武天皇のころに、
その土で、農民たちが、
生活に必要なやきものをつくったのが、
長く続く伊賀焼のはじまりだといわれています。

▲土楽の母屋。
広い敷地内には工房や登り窯、そして畑があります。
裏山にはゆずや山椒、栗などの木があり、日々の料理に使われます。
いまでも伊賀にはたくさんの窯元があります。
時代の流れか、型や機械で量産する窯もふえていますが、
土楽では、職人さんたちがろくろを回し、
手びねりで、土と語り合いながら、
時間をかけて、うつわをつくっています。

▲江戸時代に作られた工房。

▲おおきな土鍋がひけるようになるには、10年かかるそうです。
毎日使って、生活になじみ、
手になじみ、育って、
自分だけのものになっていくうつわ。
「でしゃばらず、ひかえめすぎず、
料理をひきたて、それ自身の存在感もある」
そんなうつわをつくっているのが土楽です。
現在、江戸からつづくこの窯を切り盛りしているのは、
福森家の四女である福森道歩さんです。
さかんな作陶活動を続ける
お父さんの福森雅武さんとともに、
日々、土に、火に向かっています
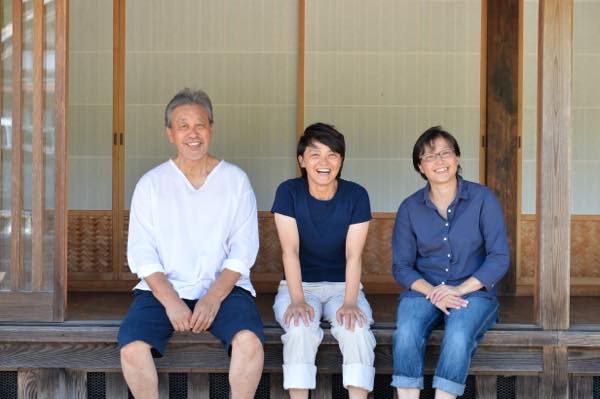
▲左から、福森雅武さん、道歩さん、道歩さんのお姉さんの柏木円さん。
「ふぞろい」ってどんなもの?
土楽のうつわは、
職人さんたちの手でつくられています。
そのため、機械でつくるうつわのように、
すべてがまったく同じには仕上がりません。
そして、やきものは火がつくるものでもあるので、
窯の中での場所や、火のあたりかたによっても、
色味にちがいがでます。それが手づくりの魅力です。

もちろん、商品として世に出るものは、
きびしく吟味されたものをそろえるのですが、
そんな中で、プロの目でなければわからないくらいの、
傷や釉薬のムラ、ゆがみ、
焼いたときに炎や灰があたったことで、
予想していなかった色みに仕上がったもの。
そんなうつわが出てくることがあります。
「規格というものは、きびしく定めて、
厳格に守らなければならない」
という目や気持ちで見たときには、
外されてしまううつわでしょうが、
使うのになんの問題もありませんし、
私たちから見ても、味のある、興味ぶかいうつわ。
「土楽のふぞろい市」にならぶのは、そんなうつわです。
「ふぞろい品」は数百種類、
飯碗、皿、鉢、湯のみなど、
土楽のすべてのラインナップからならびます。
土鍋だけでも20種類以上、サイズもさまざま。
これまで「ほぼ日」で紹介していないものも、
たくさんあります。

●黒鍋(蓋つき)
ステーキが焼ける土鍋として知られている土楽の代表作。
通常価格:尺(3〜4人用)20,520円
尺3(6〜8人用)37,800円
ふぞろい市価格は当日のおたのしみ。
●文福鍋
蒸し野菜のみずみずしい味わいをたのしめる土鍋。
通常価格:尺(3〜4人用)21,600円
尺3(6〜8人用)49,680円
ふぞろい市価格は当日のおたのしみ。
●うちの土鍋シリーズ ベア1号
黒鍋をベースに考案された「ほぼ日」コラボの土鍋。
通常価格:尺(3〜4人用)18,514円
ふぞろい市価格:11,108円
●ほんとにだいじなカレー皿
ご飯を最後のひとつぶまですっとスプーンですくえる皿。
通常価格:6,171円
ふぞろい市価格:3,703円
※価格はすべて税込
土楽のうつわや土鍋を、これだけの量、
じっさいに見て、手にとって選べる、
そんなチャンスは、東京でははじめてのこと。
土楽の地元、伊賀でも、
年に一度の陶器市にしか出されません。
しかも、いつもの土楽の価格から、
3割引きから半額ちかい値段でならびます。
土楽のやきものづくりの根っこには、
土への想いがあります。
何百万年も前、湖の底に堆積して、
やっといま、やきものの粘土になってあらわれた土。
長い年月を経て、縁あって土楽でうつわになりました。
だからこそ、うつわとしてのいのちを全うしてほしい。
使われることもなく、簡単に捨てたり、割ったりしては、
土に申し訳ない、というのが、土楽の考え方です。
気に入ったうつわに出会えたら、それも「縁」。
つくる人と、うつわと、それを選び、使う人との縁。
そんな「縁」を感じられる
「ふぞろい市」になったらうれしいと、
土楽も、ほぼ日も、思っています。

▲これは「うちの土鍋シリーズ ベア1号」。直火に強い土鍋だから、
魚の蒸し料理から、炊飯、すき焼き、おでん、パスタなど、
料理のバリエーションが広がります。

▲土楽の土鍋で焼いたステーキは、ジューシーでやわらか。
もったいなくて直火料理は怖くてできなかったというかたや、
試してみたかったけど、気軽に買えなかったというかたは、
このふぞろい市をご活用ください。
福森道歩さんはこう言います。
「人が喜んで使ってくれるものをつくる、
おいしいと感じてくださるものをつくる。
そんなうつわや料理をつくるのが、
たのしみなんです。
今回のような場では、いらっしゃるかたたちと、
ほんの少しの時間でも会えて、話ができますよね。
それは、ちょっとだけ、おたがいの人生が触れ合うこと。
それも、たのしみなんです。
土楽のうつわは、飾って見てたのしむものではありません。
台所で、食卓で、使うためにつくられているものです。
うつわのむこうには、
おいしいものを食べる笑顔が感じられる。
こんなすてきな仕事をさせてもらえることに感謝です。」

▼「ほぼ日」での土楽さんのコンテンツはこちら。
「うちの土鍋の宇宙。」
▼「土楽」の公式サイトはこちら。
https://www.doraku-gama.com/
